発達障害が疑われる状態?
部下が発達障害かもしれない、と悩んでおられる方の相談を多く受けております。
たとえば次のような部下の状態についてお困りではないでしょうか。
- いわゆる空気が読めない(指示が通らない、指示を理解してくれない)
- こだわりが強い(自分の仕事のやり方に固執し、融通が利かない)
- 自己中心的(協調性が低く、他人の意見に対して反抗的になる)
- 自分ひとりで判断をして、周りに相談できない。
- 注意散漫。仕事に集中しない、落ち着きのなさや忘れ物、物忘れが目立つ。
- 周りが困っていることに、本人は気づいていない。
- 本人は何か困っている様子だけれども、何に困っているかを報告しないため、手を付けられない。
このような状況が続いているのを見て、上司としては「発達障害かもしれない」と疑うことがあるようです。
では、発達障害が疑われたときには、どのようにすればよいのでしょうか。
発達障害への対応を検討する前に
発達障害が疑われるときには、まずは2つの対応が必要です。
- 発達障害かどうか状態を確かめる(心理アセスメントが必要)。
- 状態に合わせて、対応を決める。
発達障害と「発達障害に似たような状態」があります。
職場では「この人は発達障害だろう」と思われたとしても、発達障害ではないケースもあります。
たとえば「空気が読めない」「こだわりが強い」といわれる状態であっても、発達障害ではないケースもあります。
「発達障害かどうか」の判別は、今後の対応にもつながるので重要です。発達障害と発達障害と似たような状態では、対応が大きく異なります。
コミュニケーションが苦手という人であっても、
- 空気が読めない(発達障害)
- 空気を読みすぎて身動きが取れない(愛着障害の疑い)
では対応が異なります。
発達障害であれば「他人がどのように言葉を受け取るかを教える」ことが大切。
愛着障害が疑いであれば「まずは安心できる関係作り」が大切です。
しかしながら、状態の判別は発達障害にかかわったことのある専門家にしか行えません。
「発達障害の診断」は医師にしかできません。ただし「発達障害かどうかを調べるための心理検査(心理テスト)」は心理職の仕事です。
診断名が必要でしたら精神科医師の受診を勧めます。投薬治療も医師にしかできません。
具体的な精神状態を把握し、対応について相談したいのであれば、心理職に相談することを勧めます。心理検査やカウンセリングだけでなく対応の相談も行えます。
発達障害への対応について
では発達障害だと分かったときには、どのようにすればよいのでしょうか。
これについては、ポイントはたったひとつです。
- 本人の得意なこと、苦手なことについて、正確なアセスメント基づいた対応。
発達障害と言っても、個別差がかなりあります。
言葉で説明されるのが得意な人、図などを使って説明する方が記憶に残る人。
そういった認識能力にも得意、不得意があります。
一般的には「発達障害の人は視覚的な情報処理が得意で、構造化された課題提示が必要」とされますが、これも個人差があります。
大切なのは発達障害を抱える人は「得意なことと、苦手なことの能力の差がかなり大きい」のが特徴です。
いわゆる一般の人(発達障害ではない人の多く)は、「ある程度練習したら、ある程度の水準までできるようになる」ため、能力の差は少ないのです。
しかし発達障害の場合、「できないことはどれだけ練習しても、できるようになるのは難しい」。そのかわり「得意なことは習得が早く、場合によっては他の人よりもできるようになる」のです。
何が得意で何が苦手か。これを判別するのが心理検査(心理テスト)です。
「心理検査を受けてみないと、その人が何が得意で苦手かわかりにくい」ので対応も難しいのです。
「発達障害だと思って、特性に合わせた対応をしたけれども上手くいかなかった」という意見もあります。
しかしそういった場合「正確にその人個人の能力や精神状態をアセスメントしたのではなく」て「発達障害だったら、こうしたらいいだろう」という一般的な理論の当てはめによって対応した可能性があります。
「空気が読めない」ように見えるときでも、次のような可能性が考えられます。
- 相手が話している音声から情報を拾う能力が低い。
- 言葉の意味をあまり理解できていない。
- 話は理解できているが、自分がどのように行動したらよいのかがわからない。
- 聞くことはできていても、自分の意見を言うのが苦手。
- 1対1だと対応できるが、集団になると混乱する。
- 本人には正しい行動だと思っている。まわりとの意見の違いに気づいていない。
これ以外にも、さまざまな要因が重なって「空気が読めない」という状況が生まれます。
大切なのは「本人がどのように認識して、判断しているのか」を把握することです。
周囲が、本人の状態を把握できたとき、ようやく対応ができるようになります。
そして、こころの状態は個別差がかなりあります。個別差を把握するのは難しく、結局、心理検査や本人からの聞き取りなどの情報収集が必要です。
心理職にご相談いただければ、このような個別差について専門的に判断し、対応について提案いたします。
周囲の対応力向上を目指す
発達障害についての相談があったとき、目指すのは周囲の対応力の向上です。
こころの症状は、本人を変えようとするよりも、周囲の対応力を高める方が効果があります。
とくに発達障害を抱える人の場合は、行動パターンを変えるのが本来苦手です。
大切なのは、その個人の特性に合わせた対応ができるような職場環境を作ることです。
これは労力も時間もかかりますが、個人の能力に合わせて対応することで、離職率が下がり、仕事の生産性を高められます。
とくに障がい者雇用を検討している方々がおっしゃるのは、「発達障害の方は、特定の能力が高いのに、対応が難しい」ということです。
いいかえると「対応ができたら、高い能力を発揮できる」のです。
そのために「心理検査など専門家に基づくアセスメント」が必要です。
対応に困っておられる方は、まずは心理検査を行っているカウンセラーなどにご相談ください。個人に合わせた対応法について提案させていただきます。
Mitoce新大阪カウンセリング・心理検査では、精神科領域での経験が長い臨床心理士が、心理検査を担当いたします。これまでに発達障害の鑑別補助や、発達障害を抱える人のカウンセリングに数多く対応してきました。
発達障害について悩んでおられる方は一度、ご相談下さいませ。
Mitoce 新大阪カウンセリング・心理検査
mail: office@mitoce.net tel: 06-6829-6856
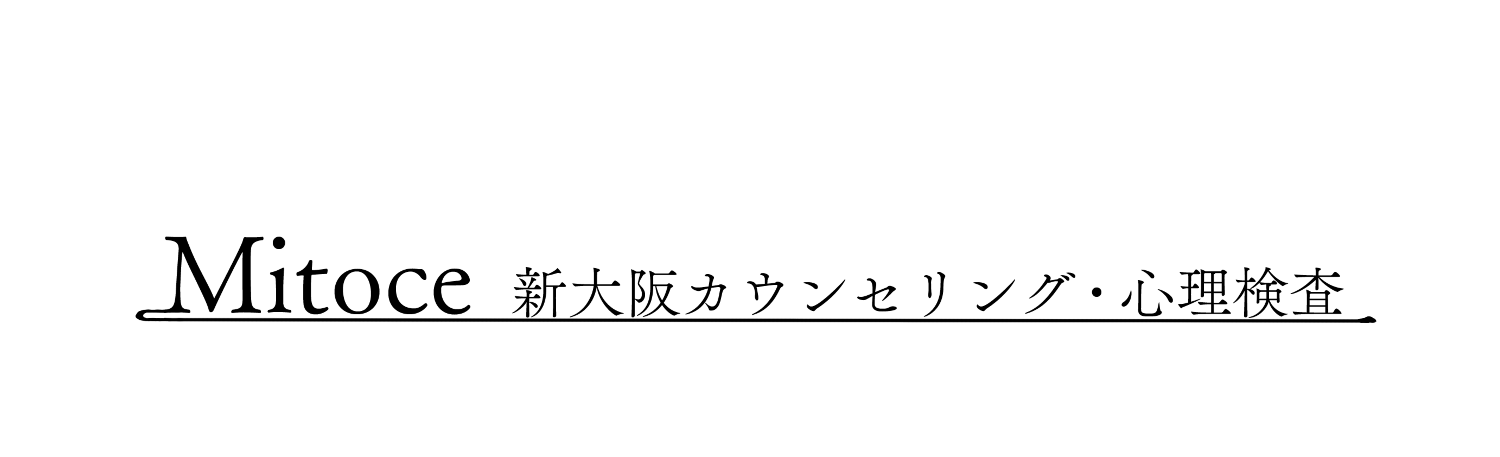

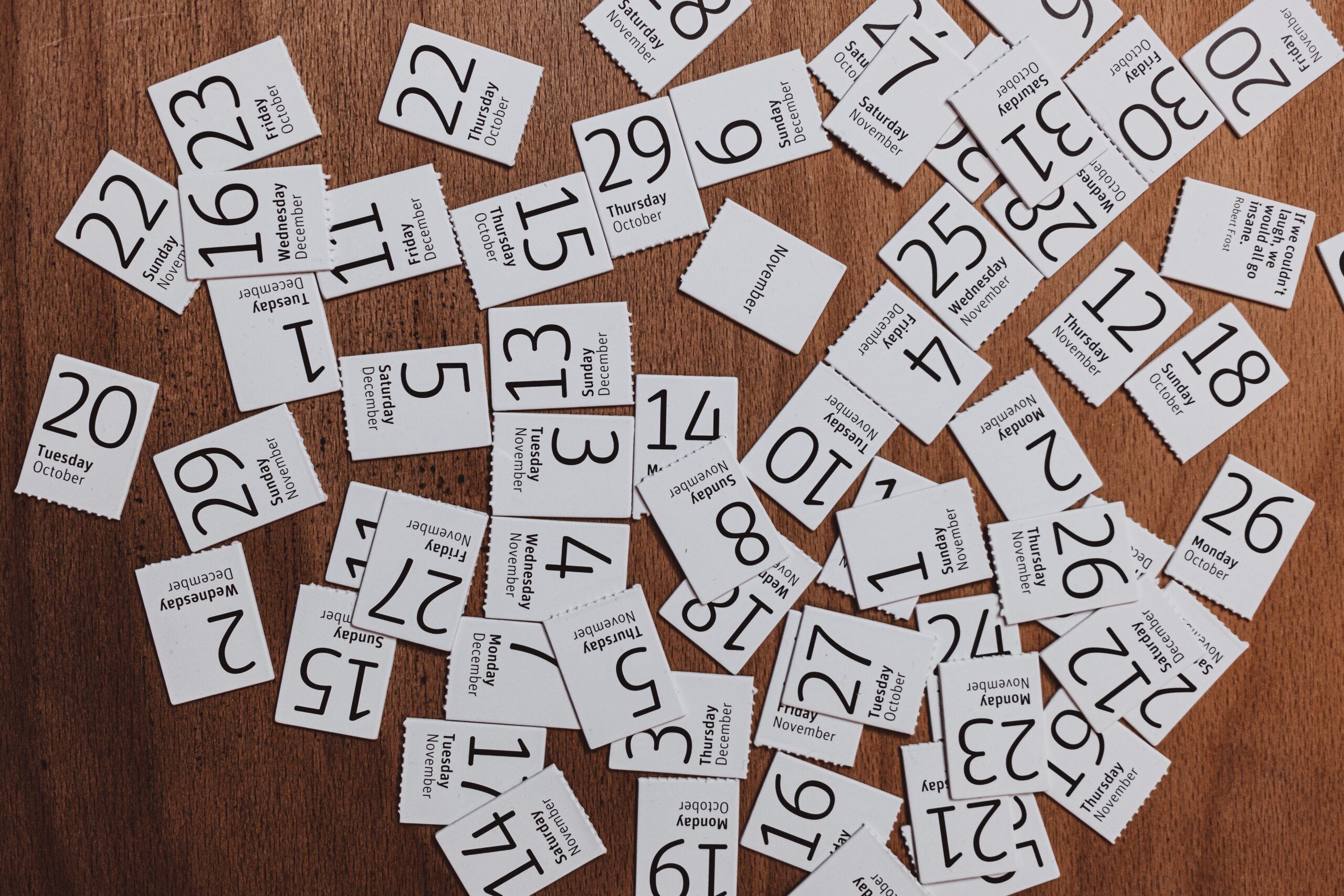

コメント
[…] 発達障害を抱えている人を取り巻く周りの人がどの程度困っているかというのは、また別の課題です。それについては「Q19. 部下が発達障害かもしれないのですが、どうしたらいいですか?」を参考にしてください。 […]