あの人は発達障害かもしれない…。
話し相手が自分の気持ちを理解してくれないとき「もしかして発達障害?」と考えたことはないでしょうか。最近は「コミュニケーションが上手くとれない人=発達障害」と疑うことが多いようです。
カウンセラーとしては「コミュニケーションの上手下手だけでは発達障害かどうかは判断できない」と思います。そのうえ良く状況をみると「発達障害だから困る」のではなくて「コミュニケーションがうまく取れないから困って」いるのです。
このような状況に対して、カウンセラーとしては「発達障害かどうか」を見るよりも、まずは「どうしてコミュニケーションがうまく取れないのか」を確認します。
そのため「あの人は発達障害でしょうか?」と聞かれた場合、カウンセラーは「どのような状況か教えていただけないでしょうか」と確認することから始めます。
発達障害だとわかっても、状況は変わらない。
もし発達障害が明らかになったとき、それだけではコミュニケーションのズレは解消されません。大切なのは発達障害の可能性含めて「何が起きているか」を明らかにして、対応を検討することです。
「気持ちがうまく通じない相手」とのコミュニケーションで何が起こっているのかを検討し、対応を考えるのが大切です。とくに気持ちを汲み取ってもらいたいけれども伝わらなかったとき、「発達障害かどうか」を明らかにしたところで不満は解消しません。それよりも「相手とのコミュニケーションにおいて何が上手くいかないか」が分かって、コミュニケーションが上手くいったとき、気持ちは楽になります。
カウンセラーのアドバイスとしては「まずは何が上手くいかないのかを検討しましょう」と提案するのは、そういう理由があるためです。
話していても「私の気持ち」を分かってもらえないとき。
「自分の考えや意図、感情を汲み取ってもらえない」と感じるとき、多くの人は戸惑います。どうすれば相手に伝わるだろうと考え、言い方を変えてみたり、表情に出したりして、相手に伝わる方法を探します。
通常のコミュニケーションでは「相手は自分の気持ちを汲み取る能力がある」という前提があります。 しかし「相手に伝わっていない」と察知すると「自分の伝え方が悪い」もしくは「相手の受け取り方が悪い」のどちらかを判断します。
そして大抵の場合は「自分の伝え方」に問題があると考え、伝え方を変えます。それで上手くいけば、コミュニケーションは円滑な状態になります。
一方で伝え方を変えても伝わらないとき「これは異常事態だ」と考え「相手の状態を察知しよう」とします。
伝え方を変えながら、相手の反応をみて「相手にこちらの意図を理解できる能力がどれほどあるか」を推しはかります。そのなかで相手との間にどのようなコミュニケーションのズレを確認します。ズレている部分が察知できれば伝え方を修正し、コミュニケーションを円滑な状態に戻します。これが通常の対処方法です。
発達障害を抱える人を相手にした場合、こういったコミュニケーションの修正という方策が役に立ちません。みなさんが対応に悩まれるのはそのような状況があるためです。
相手に思いが伝わらないとき、どのように対応するか。
相手との話がうまくかみ合っていないとき、
- こちら側の思い込み
- 相手側の思い込み
このどちらかに当てはまります。 この二つの間にズレがあると「話がかみ合わない」という状態が起こります。これは発達障害ではない人との間でも起きます。そのため、かみ合わない部分を検討し、修正することでコミュニケーションの改善を図るのです。
では発達障害の場合はどうなのでしょうか。発達障害を抱える人たちの通じなさは上の二つのうち、「相手側の思い込み」が影響していることがあります。
たとえば「話を聞いているようで別のことを考えている」「こちらの伝えた言葉を別の文脈で理解している」ことが起きやすいという特徴があります。このようなズレを修正することが対応につながります。
発達障害を抱える人と話すとき、話のずれを察知したら「今の話聞いてどのように思いましたか?」と相手がどうとらえたか確認する。これが大事なのです。
大切なのは、発達障害を抱える人であっても、コミュニケーションを工夫すると、「相手の意図を汲み取れる」人もいます。そのため発達障害かどうかにこだわるよりも、「どのようなズレが起きているのか」を把握することの方がコミュニケーションにおいて重要だといえるのです。
発達障害を抱える人のコミュニケーションとは?
参考として発達障害を抱える人たちのコミュニケーションの特徴をいくつか挙げておきます。
- 相手の反応、相手の考えを想定してない。
- 自分の伝えたい内容を一方的に話す。
- その場の思い付きで話すため、文脈がつかみにくい。
ただし、すべての発達障害を抱える人に当てはまるわけではありません。発達障害といっても、個人差があるので一概に「発達障害だから絶対にこうだ」とは言えません。大切なのは「その人がどのようなズレるパターンをしやすいか」を把握しておくことです。
このような特徴を知っておくと「どういうコミュニケーションのズレが起きているか」を把握する手掛かりにつながります。「なんとなくズレている」ではなく「どのようにズレている」か分かり、対応できるようになります。たとえば次のように言うという方法もあります。
- 「あなたの意見は分かったけれども、私の意見も聞いてもらっていいかな」
- 「今の話を聴いて、私としては不安に思ったのだけれども」
- 「話の流れとして、こういう意味だと理解してよいでしょうか」
相手が引き起こしているコミュニケーションのズレを指摘し修正する。そしてこちら側の気持ちや理解を伝える。それによってコミュニケーションの行き違いを減らすのです。
これは発達障害を抱える人への対応だけではありません。
コミュニケーションのズレは発達障害を抱える人以外でも、しばしば起きます。とくに日常的にコミュニケーションをとる必要がある相手(家族、同僚、友人など)の間でズレるとき、そのパターンを覚えておくことが大切です。ズレを減らし円滑なコミュニケーションをとることにつながるからです。これは普段、意図せず実行していることも多いでしょう。
大切なのは「どうすれば私の意図を理解してもらえるか」です。「相手は発達障害だから、私の意図を理解できるはずない」という思い込みは、先ほど挙げた、話がかみ合わないときに起きやすい、「こちら側の思い込み」といえます。
一方的に「相手にコミュニケーション能力の問題がある」と考えると、ズレは拡大します。こちらも少しずつズレを減らすことを試みる。それが発達障害かどうかを判別するよりも大切なのです。
実際にはコミュニケーションのズレを修正していくのは膨大なエネルギーを使うので、なかなか難しい。そのため「どのようにズレやすいのか」というパターンを把握することがまず目標になります。
カウンセリングではコミュニケーションのズレがどこに起きているのかを検討し、本人と確かめます。カウンセラーから説明を受けると「そのようなズレがあったのですね」と初めて理解される方も少なくありません。
身近に話がかみ合わない相手がいてお困りの方は、一度カウンセリングにご相談頂くと、何が問題として起こっているのか理解できるかもしれません。コミュニケーションにおいて何がズレているのかを整理し、こころの悩みが軽減する糸口が見つかるでしょう。
Mitoce 新大阪カウンセリング・心理検査
mail: office@mitoce.net tel: 06-6829-6856
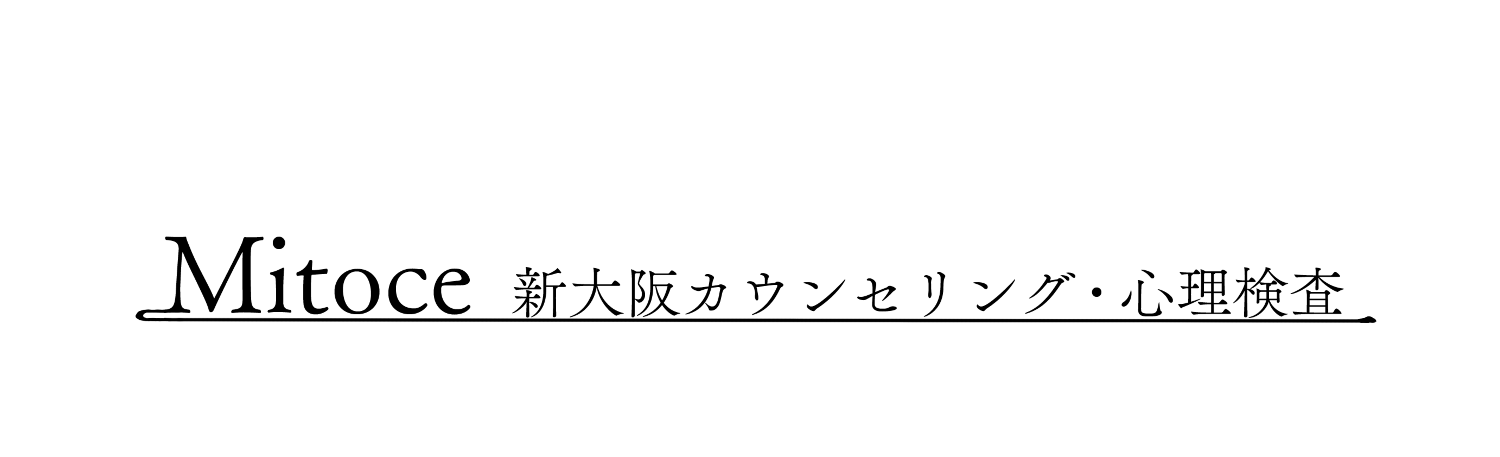



コメント