親の話し方に思わずイラついてしまう
高齢の家族が認知症を発症した。そのとき、家族の対応としてどのようにしたらいいのか、悩んでおられる方も少なくありません。
心理的な事柄に関する悩みでよくあるのが「親に話が通じなくなった」という相談です。なかでも「同じ話を何度もする」という行動は、介護する家族をイライラさせることが多いようです。
高齢の親が何度も同じ話をするので困るといいます。何回かは聞いていても、あまりにも同じ話が繰り返されるので「さっきも聞いたでしょ」と怒ってしまう。高齢の親を抱える人たちが、よく経験する出来事です。
「どうすれば親が何度も話すのを止められるのでしょうか」
そのような方法がないだろうかと、悩んでおられる家族もいます。
何度も同じことを話すことに対してイライラしてしまい、怒ってしまう。しかし、どれだけ怒っても親の行動は変わらないのです。
そういう状態が続くと家族は腹が立ってきて、イライラする。そのうち状態が変わらないことに対して、絶望的な気分になることもあります。
精神的に余裕がなくなったり、親のためも思って「親を施設に入れよう」と決断する家族もいます。
施設に入れると、ようやく平穏な生活が訪れる。かと思ったら、何かと用事があるたびに施設に呼び出されます。施設に面会にいくと、また親に小言を言われる。しかも前に結論が出たことを何度も。そのような繰り返しです。
「施設に入れたことで手はかからなくなって、少し楽になった。でも親に会ってみると話し方が変わるわけではない。会うたびにイライラする。面会はできるだけ行きたくない」
そのような経験をされている方も少なくありません。
話を繰り返すときのこころのメカニズム
年を取ると、新しいことを憶えるのが苦手になります。思考の柔軟性が減り、新しい話題についていくのが難しくなります。
柔軟性が減ると考えの切り替えが苦手になります。悩み事が出てくると、解決法が思いつかず、気がかりなことがいつまでも頭に残ることもあります。
延々と繰り返される話を、家族が聞き続けるのは難しいかもしれません。余裕があるときは聞けるかもしれませんが、解答したはずなのに、また同じ話題を繰り返す。そのようなやり取りは家族にとって負担が大きい。
話を途中で切り替えるか、話半分で聞き流すのが、現実的な対応になると思います。聴かなければならないと思って家族が無理をするほうが、長期的に見てあまり良くないと思います。
介護者である家族の負担をできる限り減らす。それが基本だと私は思います。
同じ話を繰り返すことの背景にあるこころ
では同じ話を繰り返すことについて、カウンセラーはどう考えるのかを説明します。
脳の機能低下をもちろん前提として考えますが、こころの側面からみて、繰り返される話は「その人のこころに何か引っかかっている」可能性を考えます。その人にとって大事な話だから繰り返されるかもしれないのです。
たとえば「ご飯はまだ?」と繰り返す高齢者の場合、その人にとって意味があるのと推察します。
たとえば「ご飯はまだ?」にどのような思い入れがあるか考えます。
・みんなで食べるのが好きだった。今はできなくて寂しい。
・食事を作ることが大事な私の仕事だった。家事ができなく自信を無くした。
・食べること以外に楽しみがない。
といった気持ちがあるかもしれません。
話に込められた想いを聞くこと
カウンセラーは高齢者の方とかかわるとき、まずは家族や周囲の人から本人に関する情報を集めます。そして本人がこれまでどのような人生を送ってきたかを伺います。そういった情報を集めて、その人がどのような人であったのかを確かめてから、本人に話を聞いていきます。
そこで話されるのは家族にも話しているような「同じ内容の繰り返し」だったりしますが、カウンセラーとしては「何らかのこころの動きが現れた大切な話」として聴きます。
不思議なのですが「話に込められた思い」を推測しながら聴いていると、話の内容が少しずつが変わることがあります。たとえば「ご飯はいつ?」としか言わなかったのが「今日は誰がご飯作るの?」※などです。
こういった些細な変化にこころの変化が現れるのです。こころが変わってくると、本人が以前よりも意欲が出たり、感情表現が豊かになることもあります。認知症を抱える高齢者であっても、カウンセリングは無駄とはいえません。
ただし、何度も繰り返される話に興味を持って耳を傾ける、というのは赤の他人であるカウンセラーだからできます。家族は、どうしても以前の健康だったときの様子を思い出すので、心穏やかに話を聞くことが難しいかもしれません。
対応としては、高齢の親が「何らかの理由があって同じ話をするのかもしれない」という「考える余裕」を保つことが大切です。繰り返す話を止めるのはとても難しいです。それ以前に出来ることは、まずは自分のイライラを落ち着かせることが大切です。その先にもし余裕があるときには、「同じ話を何度も聞くことで、相手の不安が鎮まるまで待つ」ことができるようになるかもしれません。
高齢の親を介護をするとき、大切なのは家族が共倒れをしないことです。親の健康状態ももちろん大切ですが、まずは家族が休憩や気晴らしの時間を設けることです。イライラは余裕がなくなっているサインです。
自分のイライラが制御できなくなっているときは、相手のために無理をしすぎているかもしれないので、相手と感情的な距離をとる手段を見つけることをまずは優先してみてください。
※「今日は誰がご飯を作るの?」という発言には、「家族と暮らしている」「家族にそれぞれ役割がある」「家族のことを気にしている」などの思いが込められています。「食事をとったかどうか」という事実確認だけではない、本人なりの思いが言葉に込められているのです。
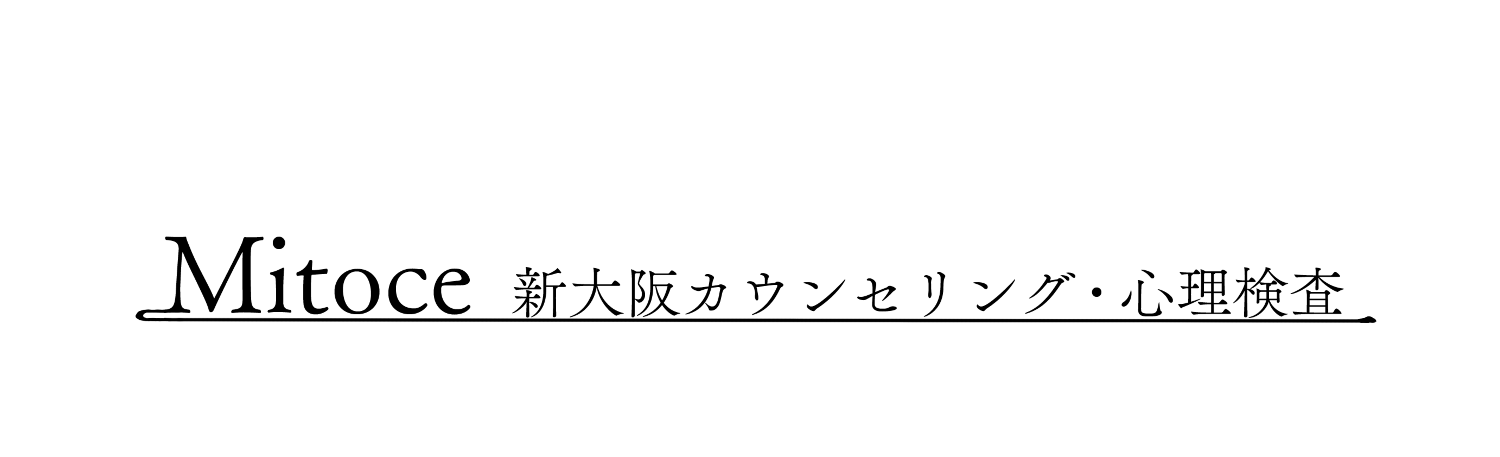



コメント