この質問は答えるのがとても難しいのですが「カウンセリングとはなにか?」にかんする本質的な問いだと思いますので答えます。
もし実際にターミナルケアを受けている方から「カウンセリングには意味があるのですか」と質問されたとすれば、私はこう言うかもしれません。
「まず、あなたについてお話を聴かせていただいても、よろしいでしょうか」
なぜそのような答えになるかを説明します。
あなたの話を聴かせてほしいという理由
入院するとその人は「患者」としてスタッフからみられるようになります。いいかえると「病気の人」になります。それまで普段の生活を送っていた「Aさん」が「患者のAさん」になります。
そして「患者A」になったときに注目されるのが「病気の部分」です。悪性腫瘍や身体の痛みなど、さまざまな症状を生み出している「病気」です。それまで「近所のAさん」のような普通に暮らしていた人が、病院では「○○の病気になっている患者のAさん」になるのです。病院のスタッフだけでなく、病気を抱えている本人も「病気」に注目するようになります。
このことが、どのような事態につながるのでしょうか。病院のスタッフや患者本人、そして家族や周りの人にとって、病気に注目するようになります。
病気の症状を軽くすること、病気の原因を見つけること、治療の成果を出すことなど、原因や結果がはっきりとしていることが重視されます。
ターミナルケアではどうでしょうか。そこでは症状をコントロールして緩やかに死を迎えることが目標になります。では「緩やかな死」はどのようにして迎えるのか。痛みや苦しみが軽減したとしても、最後には「こころの課題とどう付き合うか」という課題が残ります。その課題には原因と結果だけではとらえられない、個人的なストーリーが含まれているのです。
死を迎えるときの個人的なストーリー
たとえば数週間のうちに死を迎えようとしているある高齢の女性が「家族が心配だ」と話したとします。
スタッフが何が心配なのかと尋ねると「自分の息子は臆病で、さみしがりなんです。私が亡くなったあと、あの子はひとりでどうするのか心配」といいます。
しかしながら面会に来たその人の子どもをみると、スーツを着て、身なりも整っており、スタッフへの受け答えも丁寧です。しっかりとした印象であり、会社の役員をしていると自己紹介もされました。にもかかわらず母親からみると「臆病でさみしがりや」なのです。
なぜ母親として子どもが心配なのかをさらに聴きます。
「幼い頃に息子が高熱でうなされたとき、「お母さん」と繰り返し呼びながら、自分の手を握って放そうとしなかった」と話されます。
その印象が強く残っているのでしょう。もう60歳を過ぎた息子であっても、その人にとっては「臆病でさみしがりや」なので心配なのです。
そこには母親の息子に対する個人的な思い、いわば母子のあいだで紡がれた個人のストーリーがあるのです。
心理的な側面から考えると別の意味もみえてきます。それは幼い頃の息子に自分の思いを仮託して、自分の気持ちを伝えている可能性もあります(心理用語では投影といいます)。
「自分は一人で入院していて心細い。死ぬことが怖いし、ひとりでいるのはさみしい。だから「大事な息子に来てもらって、手をつないでほしい」という思いがあるのかもしれません。
カウンセラーに息子への思いを話した数日後です。母親の思いを察知したのか、息子さんが面会に来られたときです。息子さんがしばらくのあいだ、ベッドの横に座って母親の手を握っていました。そしてその方は緩やかな死を迎える時間をすごしたのです。
(これはあくまで実際の出来事に基づいた架空のケースです)
死を迎える人に寄り添うこころ
ターミナルケアのように死を迎えようとしている人は、病気は治らない状態にあります。そのようなとき病気を治すという目標を立てても、役に立たないことがあります。
痛みをコントロールするという効果が出る治療をしても「では痛みがおさまれば、その人はあとは死をただ待つしかないのか?」という問いが生まれます。
そのようなとき今、死を迎えようとしているその人が、どのような人生を送ってきたのか、どのように最後を過ごすのかということが重要になります。
「病気の人」というとき「病気」ではなく「人」に焦点を当てなければならないのです。
その人が一人の人間として亡くなっていく。そのときカウンセラーは「今死を迎えつつあるあなたが、これまでどのような人生を送り、どのような想いを積み重ねてきたのか。死を迎えようとするあなたのこころを聴かせてください」という心構えになります。
死を迎えるまでの過程を一人で進むのは孤独であり、不安でしょう。せめてその過程に同行させて頂けたらと、カウンセラーはクライエントの死へと至るプロセスに寄り添います。それはその人が言葉を発することができなくなっても、こころに寄り添うことは続くのです。死を迎えるまで、もしくは死を迎えても、こころは残ると考えるためです。
このような考えがあるため、私は始めに書いたような答え方をすると思います。
参考文献:『八つの人生の物語 不確かで危険に満ちた時代を道徳的に生きるということ』アーサー・クラインマン 著 皆藤章 監訳 高橋洋 訳 誠信書房 2011
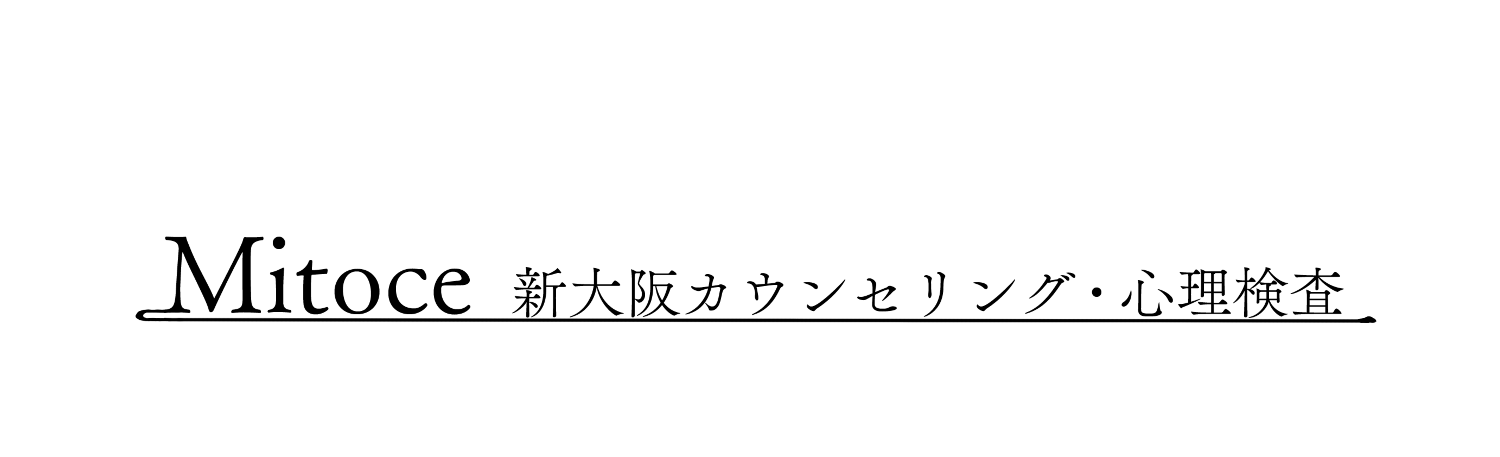



コメント