アストリッド・リンドグレーン 著 / 大塚勇三 訳(岩波少年文庫、1990年)
スウェーデンの児童文学作家、リンドグレーンの代表作『長くつ下のピッピ』。並外れて活発な女の子が、大人の決めたルールを軽々と飛び越えて大活躍する痛快な物語りです。かつてアニメ監督の宮崎駿氏が映画化を熱望しながらも、作者の承諾が得られず断念したというエピソードは有名ですが、その後の宮崎作品に多大な影響を与えたことでも知られています。
自由奔放な少女、ピッピの登場
主人公は、赤毛のツインテールに大きな靴を履いた少女、ピッピ。母親は早くに亡くなり、船乗りだった父親も航海中に嵐にさらわれ行方不明となってしまいます。ピッピは相棒のサル「ニルソン氏」とともに、かつて父が買った家へと戻ってきました。
ピッピは少し変わった女の子です。馬を持ち上げるほどの怪力を持ち、父から受け継いだ金貨を山ほど持っています。一方で、勉強は苦手でスペルも満足に書けません。しかし、彼女はどこまでも明るく前向きです。大人に頼らず子どもだけで暮らしている状況を、悲観することなど微塵もありません。
隣の家に住むトミーとアンニカという兄妹がピッピと出会い、仲良くなるところから、この物語りは動き出します。
「子どもが本当にしたかったこと」の宝庫
この物語りは、リンドグレーンが自身の娘に語り聞かせた話がもとになっています。そのためか、大人から見れば「困った子」に見えるピッピの行動には、子どもたちが「本当はやってみたいけれど、大人に止められていること」が凝縮されています。
サーカスで曲乗りの馬に飛び乗ったり、綱渡りを披露したり、力自慢の大男を投げ飛ばしたり。あるいは、お茶会のケーキを一人で平らげてしまうこともあれば、猛牛を乗りこなしたり、火事の中から子どもを救い出したりといった大胆な行動も見せます。
大人の価値観からすれば「危ない」「ルール違反だ」と眉をひそめる場面ばかりかもしれません。しかし、子どもたちにとってこれほど面白いことはありません。大切なのは、ピッピには悪意が全くないという点です。彼女はただ自分の素直な想いに従って行動しており、その無垢な姿を前にすると、誰も彼女を責めきれないのです。
「大人になりすぎて」はいませんか?
もし大人がこの物語りを読んだら、どう感じるでしょうか。破天荒な言動に「子どもが真似をしたらどうするのか」と腹を立ててしまうでしょうか。
心理学的な視点から見ると、ここで一つの問いが生まれます。 「自分は大人になりすぎてはいないだろうか?」
ピッピの振る舞いに、どこか憧れや爽快さを感じるのだとしたら、それはあなたの中に「子どもらしさ(チャイルド)」が健やかに息づいている証拠かもしれません。逆に腹を立てているときは、子どもらしさが、小さくなっているかもしれません。
あまりに「大人」になりすぎると、私たちは社会的な慣習やルールに縛られ、こころの自由を失ってしまいがちです。「これは正しいか」「世間に批判されないか」という不安に支配され、自分の本音で動くことができなくなってしまうのです。
自分らしさを取り戻すために
確かにピッピの行動は、ときとして「やりすぎ」に見えます。それは彼女を制御する大人がいないからでもあります。しかし、自由であるからこそ、彼女は大人特有の孤独感や後ろめたさに囚われることがありません。「素直に感じ、素直に動く」。その繰り返しが彼女の自己肯定感を支え、常に堂々とした佇まいをつくっています。
周りの評価を気にしすぎて、自分らしさを見失っていると感じるとき、ピッピの生き方に触れてみてください。物語りを読み終えるころには「自分もこのままで良いのかもしれない」というヒントが見つかるかもしれません。
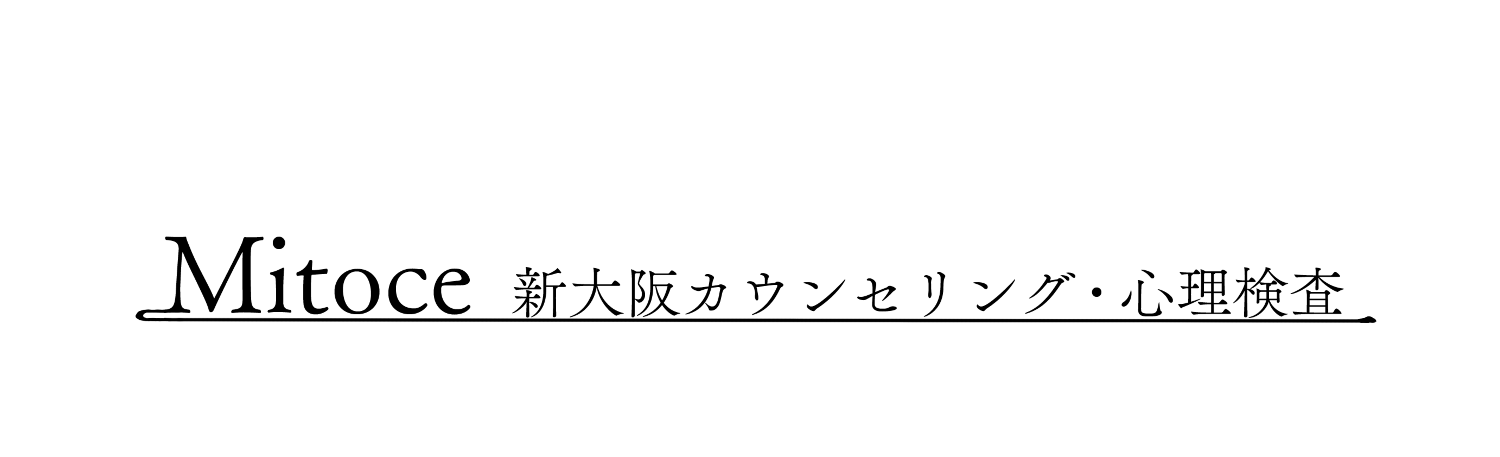


コメント