J・シュピーリ作 パウル・ハイ画 1880 『ハイジ』 矢川澄子訳 福音館書店1974
アルプスの物語の「原点」を読み解く
「アルプスの少女ハイジ」といえば、高畑勲・宮崎駿両氏が手掛けた、あの完成度の高いテレビアニメを思い浮かべる方が多いでしょう。どこまでも続く広い草原、長いブランコ、そして友人クララとの交流。スイスの大自然を背景にした物語は、今も多くの人の心に刻まれています。
しかし、その原作である『ハイジ』(1880年刊行)を大人になり、カウンセラーという仕事に就いてから読み返してみると、ある重要な事実に気づかされます。これは「こころに傷を負った人々が、いかにして癒やされ、回復していくか」を克明に描いた再生の物語であるということです。
アニメでは明るい側面が強調されますが、原作には現代の視点から見ても考えさせられる「こころのケア」のエピソードが散りばめられています。
閉ざされたこころと「トラウマ」
まず注目したいのは、ハイジの祖父、通称「アルムおんじ」の人物像です。 アニメでは多くを語られませんが、原作でのおじいさんは非常に暗い過去を背負っています。人に騙されて財産を失い、軍隊での悲惨な経験(戦闘や負傷兵の看護)を経て、さらには喧嘩で人の命を奪ったという噂さえ流れています。最愛の息子(ハイジの父)をも失い、世の中に絶望して山小屋に引きこもっている。それが彼の姿です。
現代の臨床的視点でみれば、彼は過去のトラウマ(心的外傷)の影響により、他人を信頼できなくなり、対人関係を避けてこころを閉ざしてしまった状態だといえます。周囲の人間を拒絶し、教会にも通わず、村人からは恐れられている。彼は自分を守るために、冷徹な「鎧」を身にまとって生きていたといえます。
そこへ、孫娘であるハイジがやってきます。
こころの癒し手としてのハイジ
なぜ、おじいさんはハイジにだけはこころを開いたのでしょうか。 ハイジの性格は、どこまでも真っすぐで嘘がなく、誰に対しても素直です。つまり裏表が全くありません。
トラウマを抱えた人は再び傷つくことを恐れるあまり、相手の微かな欺瞞や悪意に対して非常に敏感になります。しかし、おじいさんはハイジのなかに自分を脅かすものが何一つないことを、直感的に見抜いたのでしょう。
ハイジの純粋な存在そのものが、おじいさんのこころの鎧を少しずつ溶かしていきます。一度はハイジがフランクフルトへ去ることで、彼は再び深い喪失感と絶望を味わいます。しかし、彼女が戻ってきたとき、おじいさんは「自分にとってハイジがいかに大切な存在か」を再確認し、誰かを深く愛するという感情、すなわち他者との絆を回復させます。そのあと、彼が再び教会(村の社会)へと足を運ぶようになる姿は、自己の人生に対する信頼を取り戻した証と言えるでしょう。
しかし、おじいさんは冷静に現実も見ています。自分がこの世を去ったあとについても考えています。情に厚いペーターの家族ではなく、経済力と社会的地位のある医者やクララの父にハイジの将来を託します。これは、愛する者を自分が味わったような孤独な状況に置き去りにしないための、彼なりの願いであり、責任の取り方なのです。それは誰かを大切にすることで浮かび上がってきた、生き方だといえます。
カウンセリングの原点を見つめて
こころの変化は、心理的な要因で歩けなくなっていたクララや、盲目のおばあさんのエピソードにも共通しています。ハイジとのかかわりのなかで、こころを変化させていくのです。
日々カウンセリングの現場で、深く悩み、孤立している方々とお会いしていると、「専門家として何ができるのか」と自問自答し続ける毎日です。しかし、この物語を読み返すと、本当に人を癒やすのはテクニックではなく、ハイジのような「素直なこころ」と、ありのままを受け入れる自然という器なのかもしれないと思います。
しかしながら、現実にそのような器を果たすのは簡単ではありません。おじいさんがハイジの将来に訪れるかもしれない過酷な現実を見据えることで、ハイジを支えることになります。つまり、その人が抱える光と影の部分を受け止めなければならないのです。
私たち支援者にできることは、その人が本来持っている回復する力を邪魔しないことです。目の前のクライエントとともに自分への誠実さを大切にすること。 『ハイジ』は、こころが癒やされるとはどういうことかを、150年経った今もなお私たちに教えるのです。
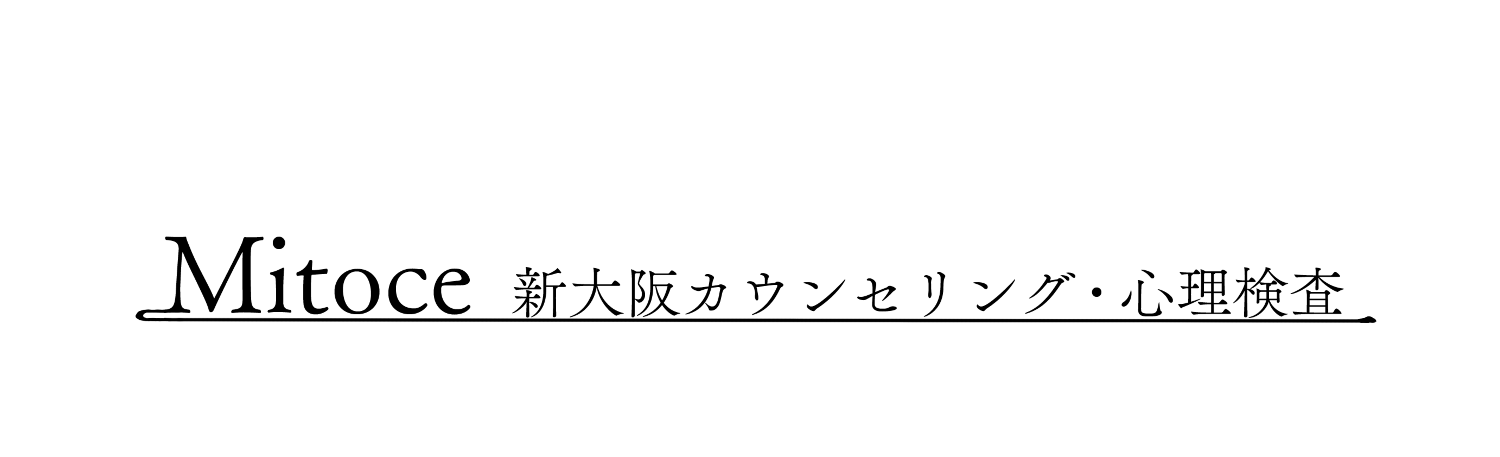



コメント