『クリスマス・キャロル』。クリスマスの時期になると、ふと読みたくなる一冊かもしれません。まずはそのあらすじを振り返ってみましょう。
主人公のスクルージは、富を築きながらも、非常に冷徹な人間として描かれます。家族もおらず、クリスマスの夜もたった一人で過ごしていました。そこへ、かつての共同経営者であったマアレイの幽霊が現れます。生前の身勝手な振る舞いを悔やみ、重い鎖に繋がれて街を彷徨うマアレイは、スクルージに「お前のもとへ3人の幽霊がやってくる。彼らと会いなさい」と告げて消えます。
その後、スクルージの前には「過去」「現在」「未来」を見せる3人の幽霊が順に現れます。幽霊とともに自らの人生を追体験していくなかで、スクルージのこころには大きな変化が生まれます。そして最後には、失っていたこころの温かさを取り戻していく、という物語です。
「冷たさ」は生きるためだった
この物語を読み進めて気づかされるのは、スクルージが他人に冷淡な態度を取るようになったのには、相応の「理由」があったということです。
幽霊とともに見る過去の経験から、彼がかつて人間関係のなかで深く傷つき、自分を守るために人を信じることをやめてしまった背景が明らかになります。つまり、彼は生まれつき冷酷だったわけではありません。人生を生き抜くための「術(すべ)」として、その態度を身に着けざるを得なかったのです。
しかし、それが彼をのちに苦しめることになるのです。
守るための鎧が、自分を縛る鎖へ
かつての友人マアレイは、自分の体を縛り付ける鎖の重さに苦しみながら、こう言います。
「生きている時に自分で作った鎖なんだ。それに今繋がれているんだ」「私はその鎖を自らすすんで身に巻き付けたのだ。自分で好んで身にかけたのだ」
幼い頃、自分を守るために必要だった「他人を寄せ付けない態度」という名の鎧。しかしそれは、大人になるにつれ、自分自身を不自由に縛り付ける重い「鎖」へと変わっていきました。しかも恐ろしいことに、その鎖は自分を縛っているだけでなく、周囲の人々をも遠ざけ、未来の自分を孤独という苦しみに突き落としていたのです。
スクルージは幽霊との対話を通じて、それにようやく気づくのです。
傷つきに「気づく」プロセス
スクルージが過去・現在・未来を直視し、苦しみの鎖から解き放たれていく過程は、カウンセリングのプロセスと非常に似通っています。
自分を縛り、生きにくくさせている「こころの構え(態度)」。なぜその構えが必要だったのか、それが今の自分や周囲にどのような影響を与えているのか、そしてそのままの自分で歩んだ先にどのような未来が待っているのか。日常のなかで、これらに自力で気づくことは容易ではありません。
カウンセリングでは自分のこころを振り返っていきます。カウンセリングのなかで自分に起きていることを見つめ直していくと、こころの奥底に抑え込んでいた本当の思いが徐々に姿を現します。頑なな態度で武装するのではなく、ありのままの自分でいられるようになる。それはスクルージの変化とも重なります。
スクルージはこころを振り返るなかで自分の素直な気持ちを表出するようになります。これは心理療法で起こる変容を似通っていると言えます。
物語のなかでは、こうした変化は「クリスマスの奇跡」として描かれています。しかし、日々のカウンセリングの現場に立ち会っていると、これは決して魔法のような奇跡ではなく、勇気を持って自分と向き合うことで誰にでも起こりうる「現実」であると実感します。
自身が何らかの「生きづらさの鎖」に縛られていると感じるなら、その鎖を少しずつ解きほぐしていくとこころの変容が起こります。鎖から解き放たれたとき、こころは新しい世界にひらかれるようになるのです。
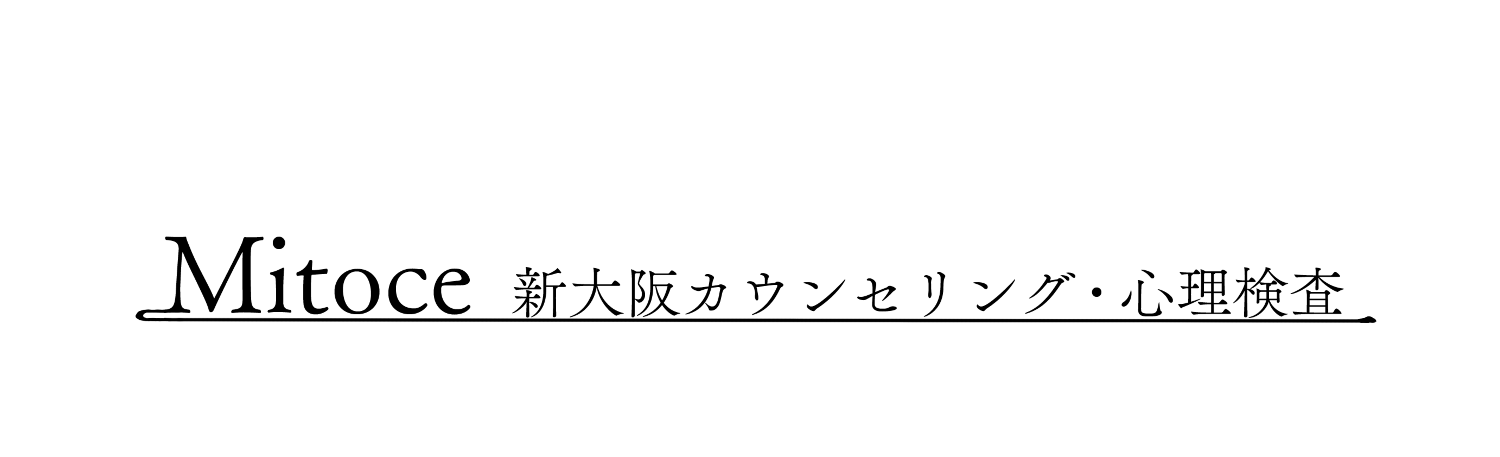



コメント