A.A.ミルン『クマのプーさん』1926 石井桃子 訳(1956)岩波少年文庫
ディズニーのキャラクターとしても有名な「クマのプーさん」。原作は、作者が自分の子どものために、その子が持っていたテディベアが活躍するお話を作ったことから始まりました。主人公のクリストファー・ロビンは、作者の息子がモデル(というより本人そのもの)です。
ディズニーの商業的な大成功により、どうしてもそちらの印象が強くなっていますが、原作を読むと、イギリスの田舎で暮らすプーさんの素朴で生き生きとした様子を知ることができます。
これまで本コラムで取り上げてきた作品と比べると、プーさんのキャラクターには、突出した際立った性格があるわけではありません。けれども、マイペースでどこかとぼけた振る舞いが、独特の可愛らしさを生んでいます。いわゆる、読んでいてほっこりする物語です。
作者が語るように、これは「子どものため」に作られた物語であり、そのことが作品を理解する大きな手がかりとなります。
子どもの役割
プーさんの行動は、なぜこれほど愛らしいのでしょうか。それは、先のことをあまり考えず、気になったことに思わず手を出しては失敗してしまう、という姿にあるのかもしれません。いわば、子ども特有の無邪気さや向こう見ずさです。
プーさんには下心があるわけではなく、ただ何かに夢中になって行動し、その結果として失敗してしまいます。そんなとき、いつも助けに現れるのがクリストファー・ロビン。彼はプーさんの持ち主である子どもですが、物語の中ではプーさんの保護者のような役割を担っています。
ここからプーさんと比較して、クリストファー・ロビンが「ほんの少しだけ大人」であることがわかります。子どもは、身近な大人との関わりの中で成長の手がかりを見つけます。子どもの読者は、クリストファー・ロビンの姿に自分を重ね合わせることで、こころをすこし成長させることができるのです。
理解者と支え
プーさんのモデルは、ミルン家にあったテディベアです(今でもその実物は大切に保管されています)。子どもにとって愛着のあるぬいぐるみは、生活をともにする信頼できる友人であり、パートナーです。楽しいこと、辛いこと、不安なこと、それらをすべて分かち合う存在なのです。
子どもの成長を願うあまり、つい「何かを懸命に教えよう」とする大人は多いものです。それも大切ですが、教えるだけでは伝わらないこともたくさんあります。この物語を読んでいると、成長のためには「失敗してもいいから、いろいろな体験をしてみること」の大切さに気づかされます。
プーさんは、穴にハマって抜け出せなくなったり、風船で飛ばされて降りられなくなったり、壺に頭を突っ込んで取れなくなったりします。しかし、それでひどく落ち込む様子はありません。それは、彼が「失敗しても許される温かな雰囲気」に包まれて暮らしているからでしょう。
人が成長するとき(それは子どもだけでなく、大人も同様です)、誰かが見守ってくれることや、共に体験してくれるパートナーの存在は不可欠です。一人きりで孤独に経験するのではなく、誰かと一緒に体験する。そして、本当に困ったときには助けてくれる誰かがいる。その安心感こそが、心の健やかな成長につながるのです。
プーさんとともに成長していく。そんな過程を楽しめる物語といえるでしょう。
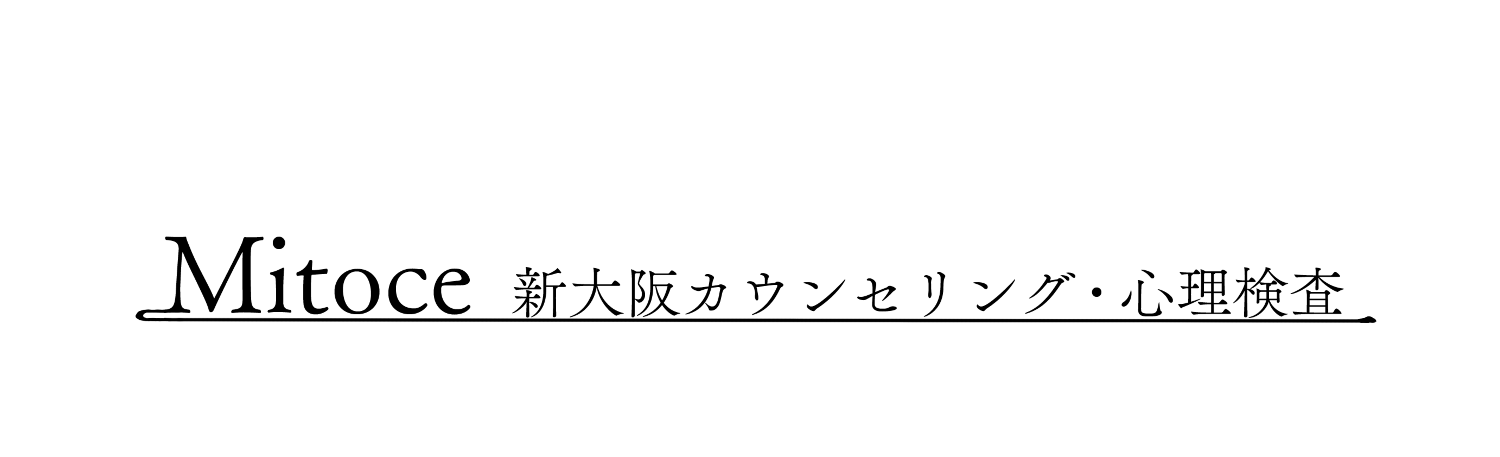


コメント