ジェームズ・M・バリー『ピーター・パンとウェンディ』(1911年)
大久保寛 訳 新潮文庫(2015年)
ディズニーアニメで有名な『ピーター・パン』。無邪気な少年ピーター、愛らしい妖精のティンカー・ベル、そして妖精の粉を振りかけられて空を飛ぶ少女ウェンディ。ネバーランドを舞台に、宿敵フック船長と繰り広げる激しい戦いなど、印象的なシーンが続く物語です。
その原作である本作を読むと、映画では語られなかった緻密な背景が見えてきます。
ピーター・パンは、心理学において「大人になれない人」を指す「ピーターパン・シンドローム」の象徴として語られることがあります。では、なぜ彼は大人になれない(ならない)のでしょうか。
大人にならないピーター・パン
一つのヒントは、ピーターがウェンディをネバーランドへ連れて行った理由にあります。彼はウェンディに、ネバーランドの子どもたちの「母親」になってほしかったのです。そこには、子どもたちを見守る「母親役」が欠けていました。
当時の社会観念からすれば、女性であるティンカー・ベルもその役割を担えそうですが、彼女はあくまで「子ども」の女の子であり、親の役割は果たせません。一方、ウェンディは年齢こそ子どもですが、家事や育児に憧れ、母親役割を担うことを望む少女でした。だからこそ、ピーターに選ばれたといえます。
ここから、ピーターが「大人になれない理由」が浮かび上がります。それは、彼を育てる「親の役割」を持つ存在がいなかったから、とは考えられないでしょうか。本作は、単に「子どもでい続ける少年」の物語ではなく、「大人になりきれなかった人々が、なぜそうなったのか」を問いかける物語とも読み取れるのです。
大人としてのフック船長
その象徴として登場するのが、宿敵フック船長です。 作中で明かされるフック船長は、実は育ちが良く、洗練された礼儀作法を身につけた人物です。それほどの教養がありながら海賊に身を転じた彼は、「社会に馴染めなかった大人」の成れの果てといえます。
心理的側面から見れば、フック船長は「ピーター・パンが否定的な形で大人になった姿」とも解釈できます。自分勝手で冒険好き、闘争に喜びを見出す性質(そもそもフックの腕を切り落とし、ワニに食べさせたのはピーター自身です)は、両者に共通しています。
つまり、二人の戦いは「似た者同士」の対決なのです。「大人になりたくない」ピーターと、「大人の社会に入らず、子どものように自由奔放に振る舞う」フック船長。最終的に、仲間を信じなかったフック船長は敗れ、仲間と協力したピーターが勝利します。通常、大きな目的を達成した人は精神的に成長するものですが、ピーターはそれを拒絶し、成長を止めます。しかし子どもたちは成長するのです。
ともに戦った子どもたちは、精神的な成長をしてネバーランドを離れ、現実の世界で大人になる道を選んでいきます。それに対し、ピーターはウェンディについていくことを拒み、一人ネバーランドへと引き返します。
大人になれない決定的な理由
ピーターが大人になれない、もう一つの決定的な特徴は、その「忘却癖」にあります。彼は驚くほど早く、過去の経験を完全に忘れてしまいます。物語の後半で明らかになりますが、彼はあんなに激しく戦ったフック船長のことさえ、そしてティンカー・ベルのことさえ忘れてしまうのです。
彼は「目の前の楽しさ」にのみ囚われて、経験を蓄積することができません。対照的なのがウェンディです。彼女は大人になり、母となっても、ピーターとの冒険を豊かな記憶として保持しています。つまりしっかりと経験を蓄積するタイプです。しかし、数年ぶりに再会したピーターは、ウェンディが大人になったことが理解できません。彼の時間は止まったままだからです。彼は成長を拒む打でけなく、成長しないともいえるのです。
この話をもとに、子どもの成長を支える「親の役割」を考えてみます。親は子どもが経験したことを見守り、記憶を共有します。「誰かが見守ってくれている」という安心できる眼差しの支えによって、子どもは自分に過去・現在・未来という時間の繋がりを知るのです。子どもにとっては、子どもの頃もわかるけれども大人の考え方も知っている。そういった親の支えによって、安心して大人になっていくのです。
大人になって読むと、ピーター・パンは「なんて手のかかる大変な子だろう」と感じてしまいます。子どもの視点に立てば、やはり拍手喝采の大英雄。読む人によって表情を変える、奥深い作品です。
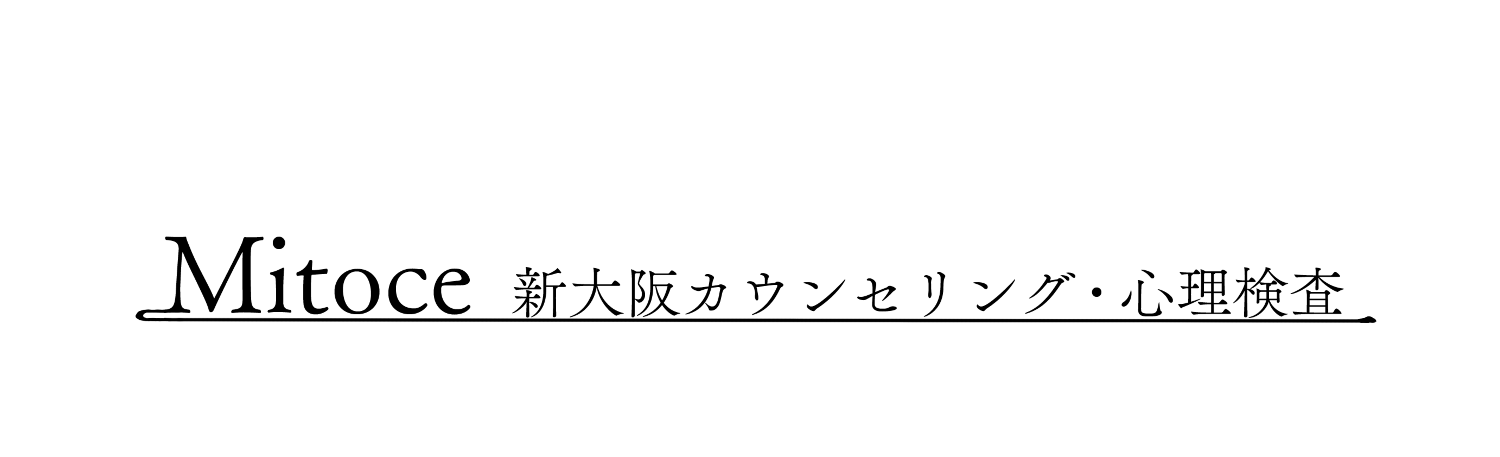


コメント