L.F.バウム作 W.W.デンスロウ画(1900年) 渡辺茂男訳『オズの魔法使い』福音館書店、1990年
映画化もされた『オズの魔法使い』。劇中で歌われた「Somewhere Over the Rainbow(虹の彼方に)」は、今もなお多くの人に愛される有名な一曲です。
原作の物語りは、アメリカの田舎町から竜巻によって異世界へ飛ばされた少女ドロシーが、そこで出会った3人の仲間とともに、魔女をめぐる旅をするという内容です。 ドロシーの仲間になるのは、印象的な3人――「かかし」「ブリキの木こり」「臆病なライオン」です。彼らとともに、ドロシーが元の世界へ戻る方法を探して「エメラルドの都」を目指すのが、この物語りのメインストーリーです。
この3人の仲間にはそれぞれ「自分には何かが足りない」という思いがあり、それが物語りに人間性を考えさせる重要な要素となっています。
かかしは、自分には考えるための「脳みそ」がないと悩んでいます。
ブリキの木こりは、自分には「心(心臓)」がないと嘆いています。
臆病なライオンは、何事も怖がってしまう自分には「勇気」がないと嘆いています。
彼らは、偉大な「オズの魔法使い」に会えば、自分たちの抱える問題が解決するのではないかと期待を寄せます。
物語の終盤、一行はついにオズの魔法使いと対面します。数々の難題(西の魔女を倒すこと)を乗り越え、ついに望みを叶えてもらえるときが来ました。しかし、そこで明らかになったオズの正体は、実は魔法は一切使えない、奇術師(サーカスの手品師)でした。
正体を見破られたオズは、3人にこう語りかけます。 「脳みそなんていらない。毎日何かを学んでいるのだから、経験を積めば知識はつく」 「勇気はすでに持っている。怖くても危険に向かっていくことこそが勇気なのだ」 「心は人を不幸にすることもある。心がないのはむしろ良いことだ」
しかし、3人は納得しません。 そこでオズは別の方法を考え出します。
かかしの頭にはもみがらを詰め込み「脳を入れた」といい、木こりにはおがくずを詰めた絹の心臓を与え、ライオンには「勇気が出る液体」を飲ませたのです。いわば3人を「騙した」とも言える行為でしたが、彼らはそれによってようやく納得しました。
興味深いのは、そのあとの展開です。3人はさらに続く旅路で、実際に知恵のある行動をとり、心を大切にし、勇気ある振る舞いを見せるようになります。つまり、3人は変化したのです。
この一連の流れは、カウンセラーとして深く考えさせられるものがあります。
足りないわけではない
カウンセリングには、さまざまな悩みを抱えたクライエントが来られます。 「自分は頭が良くないからできない」「性格や心の状態が悪い」「勇気がないから一歩が踏み出せない」 こうした悩みは、実際の相談場面でもよく見られます。
悩みを伺っていると、現状として物事を的確に判断されていたり、豊かな感情を持っていたり、勇気が必要な場面でしっかり行動されていたりすることがあります。つまり「本人がそう思い込んでいるだけ」で、実際は異なるという側面が見えきます。
しかし、そこで「あなたは充分物事を理解しているし、こころも健康です。自信がないようですが、実際にやってみれば大丈夫ですよ」と助言をしたとしても、本人はなかなか納得しません。
『オズの魔法使い』の3人のように「自分が納得できる何か」を必要としていることがあるからです。それは他人の言葉ではなく、「自分が変わった」と実感できる具体的な手応えの場合もあります。たとえば「試験に合格した」「資格を取った」「何らかの成果を得た」という、目に見える形を求めていることもあるのです。
客観的には、それらを手に入れられたのは「もともとその力が備わっていたから」だと言えますが、本人にとっては「新しく手に入れた」という感覚こそ大事なのです。次の一歩を踏み出すための「証明書」のような役割を果たすのかもしれません。
また、資格や成果を得ることで、すべてが解決するわけではありません。そのあとに「実際に資格が役に立った」「手に入れたことで生活が変化した」という実体験を重ねることで、ようやく「自分には判断力がある」「勇気が出せるようになった」という感覚が定着していくのです。
人間が成長し、変化していくプロセスを考えると、私たちカウンセラーの助言はあくまで「入り口」や「きっかけ」に過ぎないのに気づきます。大切なのは、クライエント自身が「自分は変わった」と納得できる実感を、現実の世界で積み重ねていくことなのだろうと感じます。
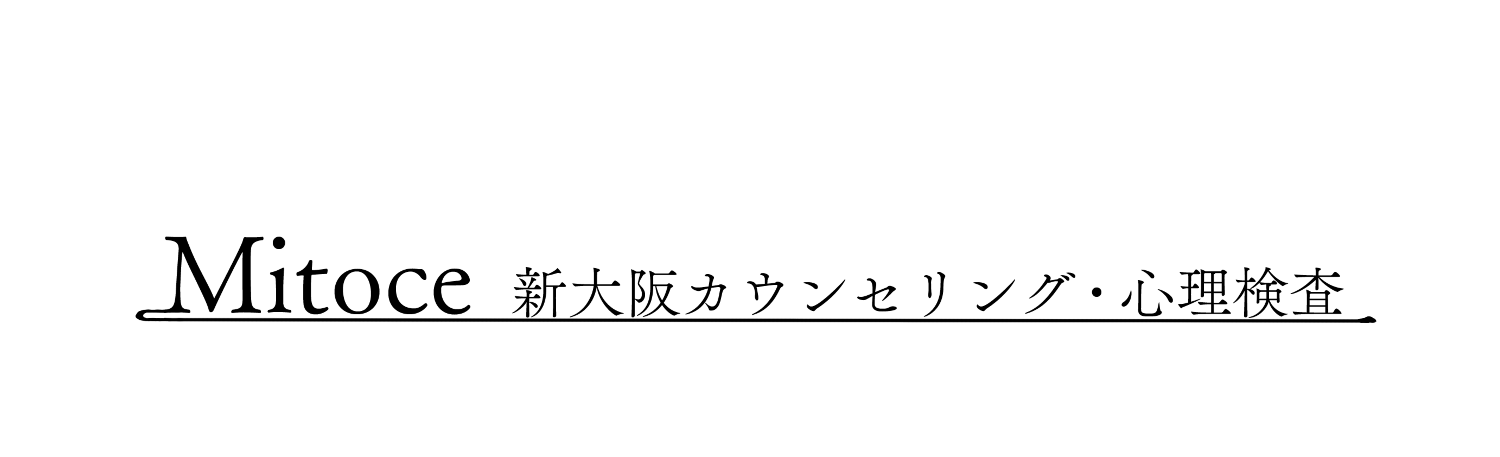



コメント