カウンセリングを広めた立役者
日本におけるカウンセリング文化の基礎を作った河合隼雄。文化庁長官を務め、臨床心理士資格の設立および発展に寄与した人物です。日本人のJung派分析家の第1号であり、分析心理学に基づく心理療法およびスイス留学中に学んだ箱庭療法の普及にも尽力しました。スクールカウンセラーが日本で広まったのは、河合隼雄の功績が大きいといえます。
河合隼雄の著書は心理療法の専門家以外にも広く読まれており、今回取り上げる『こころの処方箋』は現在も版を重ねています。カウンセリングに関心を持っている人にもぜひ読んでもらいたいため、今回、紹介することにしました。河合隼雄らしい物言いを体験してください。
人のこころは分からない
カウンセラーは人のこころがわかるのでしょうか。そのような質問を受けることがしばしばあります。一般的にも「心理学を学んでいると人のこころがわかる」と思われるようです。私も「カウンセリングをしている」と自己紹介をすると、「じゃあ、私のこころが読めるんですね」といわれることがあります。しかし実際には、カウンセラーであっても、人のこころはわかりません。というよりも、むしろ「わからない」ことを大切にすることが専門家といえるかもしれません。
河合は次のように言います。
人の心がいかにわからないかということを、確信をもって知っているところが、専門家の特徴である
初めて読んだとき、私にはこの一節の意味がよくわかりませんでした。しかしカウンセリングという仕事を続けているうちに、たしかにそうだろうなと思うようになりました。
心理学を勉強していると「人のこころはこんな特徴がある」という知識をたくさん得ることができます。しかし「人の悩みにかかわる」というカウンセリングの現場では、本で得た知識だけでは対応できないこと、つまりどうしたらよいかわからない事態が頻繁に起こってきます。というのも、悩み事というのは人によって千差万別で、誰として同じ悩みは抱えていないからです。いわば、それぞれの個性や生き方によって悩み事は異なるので、「こうすれば、こうなる」というマニュアル的な知識では対応できないのです。
たとえば、「私は発達障がいだと思います。発達障がいの対応法ってありますよね。教えてください」といわれても、「そもそも発達障がいか、どうかもわからない」「発達障がいと診断された人であっても、それぞれ個性があるので個別の対応が必要」なのです。つまり発達障がいにはこのような対応をしたらよい、という知識があっても、その人に合った個別の対応が出来るわけではありません。カウンセリングは常にオーダーメイドの対応が求められるのです。
河合は続けて言います。
速断せずに期待しながら見ていることによって、今までわからなかった可能性が明らかになり、人間が変化してゆくことは素晴らしいことである。しかし、これは随分と心のエネルギーのいることで、簡単にできることではない。むしろ、「わかった」と思って決めつけてしまうほうが、よほど楽なのである
さきほどの「わからない」ことを大切にするのは、セラピストが即断しないでクライエント自身で変化していくことを支えるためだといえます。セラピストが答えを出して「わかってしまった」かのような対応をすると、さきほど説明した、その人らしい解決方法や個性を育てる機会を奪ってしまう可能性があります。悩みを相談に来たクライエントは、自分らしい個性を見失って悩んでいる人も多いので、簡単に「わかってしまう」ことは課題の先延ばしになるだけで、本当の解決にはならないのです。
つまりこころの課題をどう解決していくかは、クライエント本人が「自分がこういう原因で悩んでいる」という表面的に理解できる部分だけでなく、「こんなこともあったと気づいた」という深い部分での理解も大切なのです。「わかった」という体験は、教えられたからわかるのではなくて、自分で気づいて本当に納得がいったときに生まれるのです。
それはクライエント自身でもわからない事柄なので、そもそもセラピストが分かるはずはありません。というのもセラピストは本人から聴いた話の内容から判断します。話を聴きながらある程度は「こんなことがありそうかな」と予想はできても、具体的な答えまではわかりません。いいかえれば、答えはクライエントのなかにあるのです。セラピストはクライエントに正解を伝えるのではなく、クラインエントが自分で答えをみつけるためのサポートをするのです。
クライエントが自分で答えを見つけ、自分の力で悩みを癒していく。このことを河合隼雄は処方箋という言葉を使って説明します。
「心の処方箋」は「体の処方箋」とは大分異なってくる。現状を分析し、原因を究明して、その対策としてそれが出てくるのではなく、むしろ、未知の可能性の方に注目し、そこから生じてくるものを尊重しているうちに、おのずから処方箋も生まれでてくるのである
クライエントのこころのなかから生まれてくる、変化の可能性。それは初めは未知の状態でしたが、こころを深く掘り下げていくと、少しずつ明らかになってくる。それが支えるのがカウンセリングなのです。
変化の可能性は否定的な姿で現れる
こころの変化はどのように現れるのでしょうか。
カウンセリングを続けることで、しばらくするとクライエントが「悩みが軽くなった」「気持ちが整理できた」とおっしゃることがあります。しかし、こういった変化は、カウンセリングが進み始めると自然と起きてくることであり、それはまだ、こころの変化のほんの入り口なのです。「良くなった」と思っていたのが、かえって難しい問題が明らかになることもあります。
河合は言います。
「ふたつよいことさてないものよ」
良い出来事が起こったとしても、不思議とその裏側には大変苦しい課題が潜んでいることがあります。こころが大きく変化する。それは表面的な問題の解決だけではなく、深い部分での問題解決が起きたときです。それは単純な「こうすれば良くなった」というマニュアル化できるような解決ではありません。自分自身の課題に全身で取組んで、そのなかでようやく見えてきた小さな手掛かりを手繰る先に、ようやく到達できるのです。こういった人が変わるには時間も労力もかかります。
そのような事情をふまえてか、河合は次のように言います。
「ふたつわるいこともさてないものよ」
こころの内的な世界から見ると、良い悪いについて簡単に評価できない出来事がほとんどです。それどころか、こころが変わるきっかけの多くは、一見悪いことから始まるといえるかもしれません。悩み事というのはクライエント本人の意識にとってはマイナスなのですが、こころが大きく変わるきっかけとなるという側面からみるとプラスともいえます。
ただし、苦しみのなかにある「自分の成長にとって肯定的な側面」に気づくのは、相当難しいです。セラピストはクライエントの苦しみや悩みを知っているからこそ、困難な状況であってもクライエントの成長に付き添うことが出来るのです。
自分には創造力がない、考える力がない、想像する力もない、行動力もない。そういった訴えをするクライエントもいます。実際にはそのような訴えをするクライエントであっても、きっかけがあれば大きな創造性を発揮することがあります。それを知っているからこそ、セラピストはクライエントの悩みにかかわり続けられるのです。
河合隼雄の本は、専門家ではない人にも読みやすい記述にあふれています。読みやすさの裏には、こころと深くかかわるカウンセリングの実践に裏付けられた、洞察が含まれています。自分のこころに真摯に向き合おうとしているとき、この意味に気づくことがあるでしょう。こころを深いところで知りたい、カウンセリングを受けたいと思ったら、一度ご相談ください。こころの世界を旅するサポートをいたします。
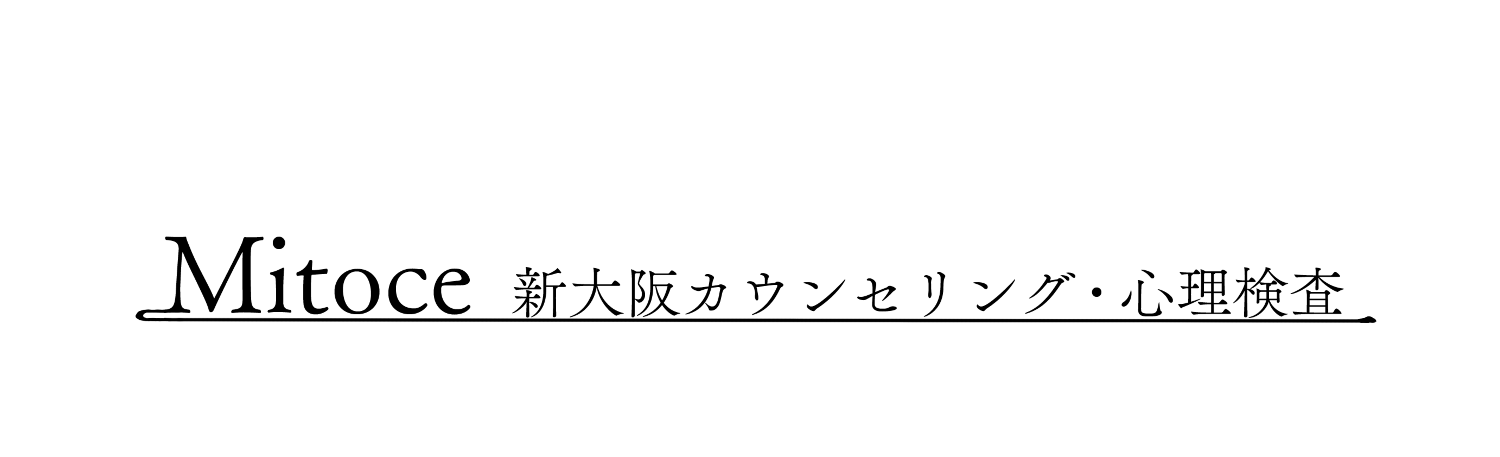



コメント